3月25日に開催された類塾×ひきたよしあき特別講演会「親も子も話すこと、書くこと、自分が好きになる!〜言葉のマグネットで自分の言葉の世界をひろげよう〜」に先立って行われた、ひきたよしあきと、齋藤 仁巳 先生(株式会社類設計室 教育事業部 次長/文系講師)、山根 教彦 氏(株式会社類設計室 経営統括部 経営企画課長/人材課長)との鼎談のもようを、5回にわたってお届けします。
言葉、教育、次世代育成…多くの共通点を持つひきたよしあきと類設計室の教育事業(類塾)。物事の本質や根源、すなわち「本源」にまでさかのぼって課題を追求することを大切にしている両者の考える教育、勉強、読解力とは? ほかでは聞けない貴重なお話がたくさん出ました。
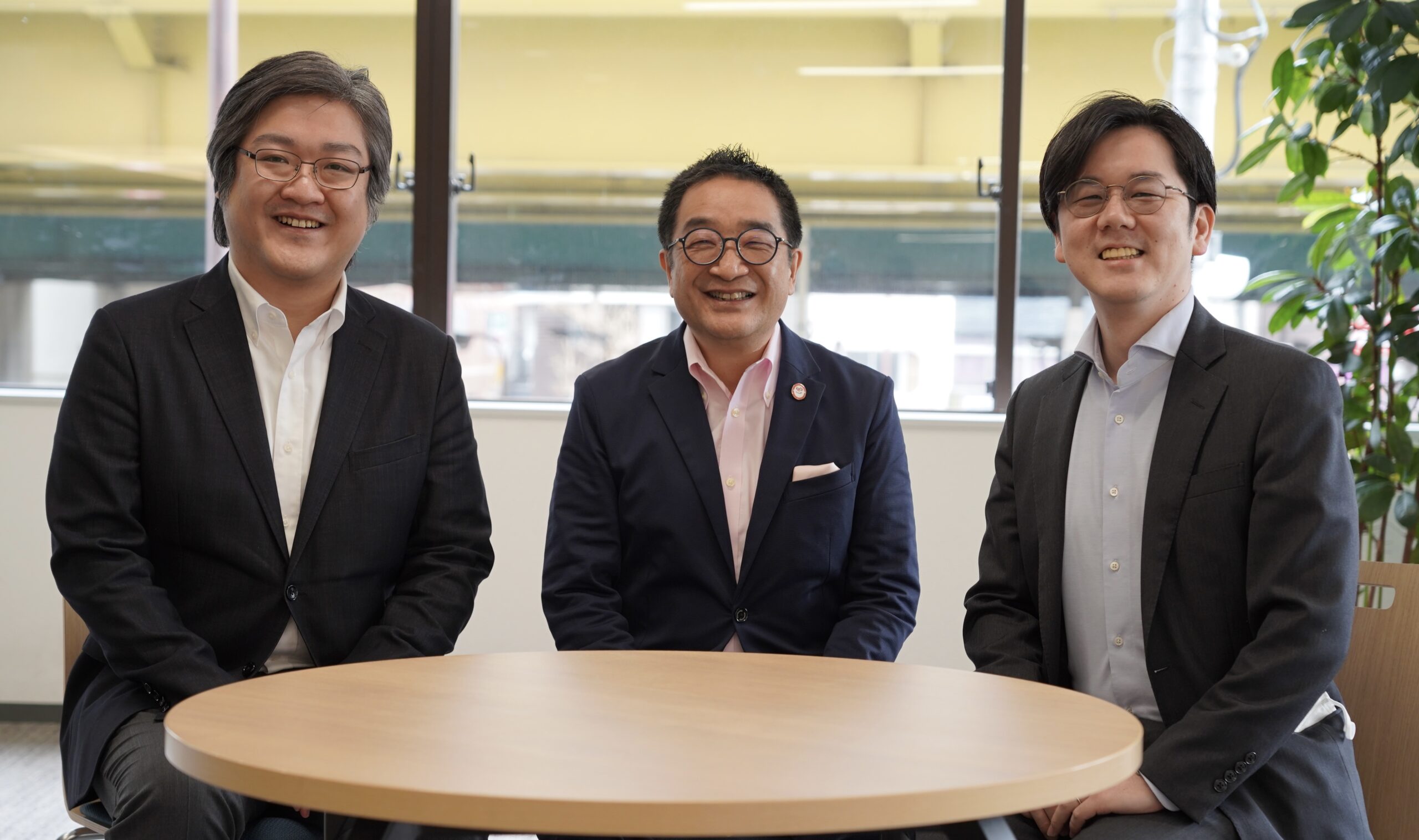
【目次】
第1話 入試の先にある言葉の使い方/体験のストックをして、そしてそれを考えた経験があるか ←いまココ
第2話 親は自分の子の良い点を探す力が発揮できているか/エールを贈る
第3話 探求しよう/シンプルに自分が思ったことを書けることがだいじ/社会の中での読解力も身に着けたらもっと楽しくなるよ
第4話 言葉を駆使して生きる力/体と心と頭がつながった言葉/大谷翔平のどこが素晴らしいかということを僕たちは教えていかないといけない
第5話 イタリアの校長先生の言葉/好きな色を自由に決められることが勉強/みんなが笑って暮らせる国へ
■■入試の先にある言葉の使い方/体験のストックをして、そしてそれを考えた経験があるか■■
――今回の講演は準備に半年間かけられたと聞きましたが、どのようなところから企画が始まったのですか?
ひきたよしあき(以下、ひきた) 僕は以前から類設計室さんのお仕事をお手伝いしていたんだけど、類塾のパンフレットやホームページをリニューアルしようという話が出た。ちょうどそのとき、類塾をこれからどういうふうにしていくかという変わり目だったんです。それで僕が「朝日小学生新聞」や博報堂財団などで子どもと関わる仕事をしているので、そんなノウハウを話しているうちに山根さんから「一度子どもたちに向けて講演をしてくれませんか?」と言われたのが始まりですよね。
山根 教彦 (以下、山根) 私はもともと東京の類設計室にいたのですけど、そのころから設計プロジェクトのコンセプトメイキングやコピーの打ち出し方などを、ひきたさんに相談させていただいていました。その後、大阪勤務になって広報の役割も担うことになったので、今度は類設計室という会社のブランディングを考えるにあたり、引き続きひきたさんにいろいろ相談させていただくことになったんです。そのときに、弊社のこの類ビル(大阪)の3階にある「類学舎」という半業半学の全日制スクールをひきたさんに見学していただきました。
ひきた 実際に授業に入って、子どもたちに混じって彼らの討論とか聞いたんです。めちゃくちゃ面白かった。
山根 ひきたさんが子どもたちの中に入っていってかけていただく言葉に、子どもたちの反応がとても良かった。それで、講演のご相談をしたらご快諾いただけて。そのときに聞いた話をみんなにもしてもらえたら、ウチにとっても刺激になるんじゃないかな、という思いもありました。

――そのときは何年生の授業を見学されたんですか?
山根 類学舎は小学生から高校生までいるんですが、そのとき入っていただいたのは中学生の混合クラス。中学1年生から3年生までが一緒になって、ある一つのテーマについて議論するという授業だったと思います。
――齋藤先生は国語の先生ですが、何年生を教えているんですか?
齋藤 仁巳 (以下、齋藤) 基本的には5歳から中学校3年生までなんですけど、一時は高校3年生まで見ていました。
ひきた 18歳?5歳から?
齋藤 はい。そういう時期もありました。いまは中学生までです。
――それでも5歳から15歳まで。10歳差は難しくないですか?
齋藤 いや、基本的には変わりません。使う言葉は変わってきますが。私は今日ひきたさんから学びたいことがあって、なにかというと、子どもの、心から出てくる言葉はやっぱりいちばん面白いんですが、言葉というのは当然ながら言葉という形になってしまう。それをどういう形にしていくかとか、ときには形にしないほうがいいこともある。そのあたりを、プロであるひきたさんに、子どもたちから出る言葉をどういう位置づけで、社会との距離感をどう取るかすごく学びたいんです。
――真面目ですね。
齋藤 真面目ですか?
山根 最初に真面目が出ちゃうタイプ(笑)。
齋藤 最初に真面目が出るって、なんですかそれ(笑)。
ひきた (笑)最近、心の内面をあまり言わないで、表の言葉のようなもので話そうとする子が多くなってきていませんか?

齋藤 そうですね。出し方がわからないのか。以前もひきたさんに相談させていただいたんですが、まねる対象が少なくなってきてしまっているのかとか、ご家庭での会話も含めて、そういうふうに気持ちを交わす機会が減っているのかなとかいろいろ考えますね。
ひきた なんか表面的な、「誰も傷つけないけど自分の内心でもない」みたいな言葉でうまくやっちゃう子どもが多くなったような気がしますよね。傷つけないように、傷つかないようにっていう言葉づかいがものすごくうまくなってきていて、そのぶん本音とかが書けなくなっている子どもが多くなってきている。
だから作文なんかも早くうまく書くんですけど、深みがない。昔みたいにめちゃくちゃヘタな子はいないんですよ。僕が授業をしたあとに感想とかを書いてもらうと、そこには批判的な感想はなくて、みんな好意的なことを書いてくる。初めのうちは「あ、オレめちゃくちゃ講義ウケたな」とか思うんだけど、どこに行ってもだいたい同じような内容になってくると、「あ、こういう書き方を学校の先生から学んでいるんだな」と思うよね。
――齋藤先生は国語を教えていらっしゃる中で、そのような状況についてどうお考えですか?
齋藤 それはそれとして否定をしてもしようがないので、自分の授業ではまずは感情をそのまま出すことや、自然体で感じたことをそのまま、どんな言葉ででもいいから出すということを取り入れていて、そうして話し言葉で気持ちを喚起した上で書き言葉にするということをしています。そういう過程を取ると「こんなふうに書いてもいいんだ」「ストレートに出してもいいんだ」と子どもたちが感じるみたいです。本音、本音とよく聞くけど、「こう書くものや」と頭の中で決めつけてしまっていたら、本音を出していいと思ってもらえるようになるまでが難しい。
ひきた 国語の教育が一時期、三択の中から選ぶというのがあったじゃないですか。「そのときの主人公の気持ちを3つの中から選べ」みたいな。我々は作る側だから正解と、2つの不正解の答えを作るんだけど、そういう教育をしていくと子どもたちは答えは1つだと思うようになるんですね。そして、先生は答えを持っているものと考えるんです。そうすると、その答えを聞きたがるんだけど、本当はそんなことはなくていくらでも解釈があっていいわけです。だけど、1つの問題に対しては答えが1個あるという教育がされている。類塾さんがやっているみたいな、本音を出すとか言いたいことを言うというのは、あんまりやらない。それはどうやって教えているんですか?
齋藤 たとえば入試問題だとピンキリある。やはり優れた学校や問題作成者は、本質的な答えがだいたいしぼることができるところまで選択肢を用意していたり、出題がされているので、入試対策の国語もおのずと伝える内容が変わってきます。
おっしゃるように選択肢の答えって100点満点ではなくて、20点、40点、60点の選択肢があったら60点を選ぶんだよという話だし、20点でもまったくの間違いではないということ、それから、入試のもっと先にある、社会に出たときに正解のない人や現象に応じて、相手も喜ぶ、満足できる言葉の使い方ができるようになろうというのは、いちばん伝えています。
ひきた そこだいじですよね。いわゆる入試の答えや正解を出すのではなく、臨機応変に社会の中で相手のことを考えた言葉を出していく、そして自分の本音を出していくという、これはいまの教育では難しいというのが、正直なところなんじゃないかなと思います。
僕は自分の本が入試問題に使われることがあるのだけど、その入試問題を僕は解けない(笑)。なぜこれはこんなに難しいんだろうと思うと、全然違うところから引っ張ってきてその解を見出してきている。作者自身はそんなことは思ってない、というのがあったりしてね。だからあれはもう、ある種のゲームになっているところがある気がするんですよね。僕からするとそのゲームの勉強をしたところで読解力がつくとは思えない。それを超えた教育というものを考えていくと、読むとか書くというのはすごくシンプルにやっていかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、そのへんはどうですか?
齋藤 どうすれば読解力はつくのかというのは永遠のテーマです。自分の子どもに対して、物事を理解する力や、文章を読んで頭に入れる力がないんじゃないかと不安に思っている保護者は多い。子どもたちも、自分は文字が嫌いだから読解力がないと思い込んでいる。その読解力をつけていくうえで、講師は何がいちばん重要なのか、どんな姿勢を子どもたちに見せるのがだいじなのかというところもお伺いしたいです。

ひきた 読解力というのは、本を読んでその内容を理解する、ということだけではないと思うんですね。実世界での経験と本の中で出会ったときに「ああ、自分とおんなじだ」って思う、ここまでいって読解力だと思うの。体験と読書がくっついている。日常生活での経験が乏しくて、その中で主人公なりの体験を読み込もうと思っても無理だと思うんだよね。
たとえば、農作業の苦しさを知っている人と知らない人が同じ本を読んだとして、その中で農作業の重労働のつらさの描写が出てきたときに理解度が違う。それは本の読み方が全然違うから。だから、日常の中でどれだけ体験のストックをして、そしてそれを考えた経験があるかということと読書は結び付いていると思うんですよね。
(解剖学者の)養老孟司さんが昔、農業体験を子どものころにさせろと言っていたんですけど、それは、たとえば田植えをするじゃないですか。すると田んぼに入ると、土の柔らかさ、水の冷たさ、不安定な感じというのがありますよね。あの瞬間に、脳は生きようとしてやたらに働くらしいんです。あぜ道を歩けば、砂利がぶつかったり砂利に足が取られたりしますよね。そうすると、そこでもまた脳は一生懸命働く。子どものころにそういう経験をすることが、脳にとってはものすごくだいじなんですね。そういう経験がなく、空調の効いた平坦な道を歩くというのは、生きようとする進歩がないわけです。そういう中で読書をしても、脳は発達しないと言うんです。だから、子どものころにいろんな体験を覚えさせることは読解力に必要不可欠だと思うんですが、これって類塾さんの教育にけっこう近いんじゃないかなと僕は思っています。
山根 ちょうどわれわれも4月に「自然学舎」という事業を立ち上げて、茨木市と箕面市の丘陵にまたがる彩都という場所にに弊社が持つ山林があるのですが、そこに江戸時代から残っている棚田があるのでそこで農作業と、あと山での体験を子どもたちにしてもらっています。一回きりの体験ではなく、継続的に、何度も何度もそこで試行錯誤して、葛藤や挑戦をしてもらっています。
この間も中2の子が悲しそうにしていたのですが、聞くと、自分が作っていた作物が鹿に食べられたと言う。だから獣柵というのは必要なのだということを学習して柵を作ったんですよね。そういうリアルな体験というのは、収穫イベントなどでは学べないことを学べるのだろうなあと。こういう活動をこの4月から拡大させて、類塾の学びとつなげながらやりたいと思っています。

ひきた そこはすごくだいじだなと思っていて、たとえば田植え体験やりました、稲刈り体験やりましたというのが、イベントとしてやるだけだと「ああ、楽しかった」で終わるけど、本当は途中の草むしりが大変だったりするわけじゃないですか。でもその草むしりは、いままでの教育ではなかったりするわけですよね。そういう不完全な体験で読書をしたところで、情報処理はできるけど読解力にはなっていかないんじゃないかという気がするんです。
齋藤 さきほどおっしゃられた「不安定なものに触れた瞬間に脳が反応する」ということがだいじなんだと思うんです。私は不安定な状態になるって悪いことではないと思うんですけど、いまの子たちって身体的にも心的にも不安定な状態になることは悪いことだと考える傾向がある。
山根 異学年で教育しているのも、同世代だけだと多少の差が不安につながったりするんですけど、いろんな学年がいると「あ、先輩にはこういう人もいるし、こういう人もいる」というような学びもあると思ってて。これってよくひきたさんがおっしゃる「心理的安全性」がある状態だと思うんですけど、そういう心理的安全性の中で自分を出していいんだという感覚と、さまざまな場所での豊かな体験、そして最後に言葉を学ぶ、それがちゃんとつながると言語能力というのはすごく伸びていくのかなと思います。